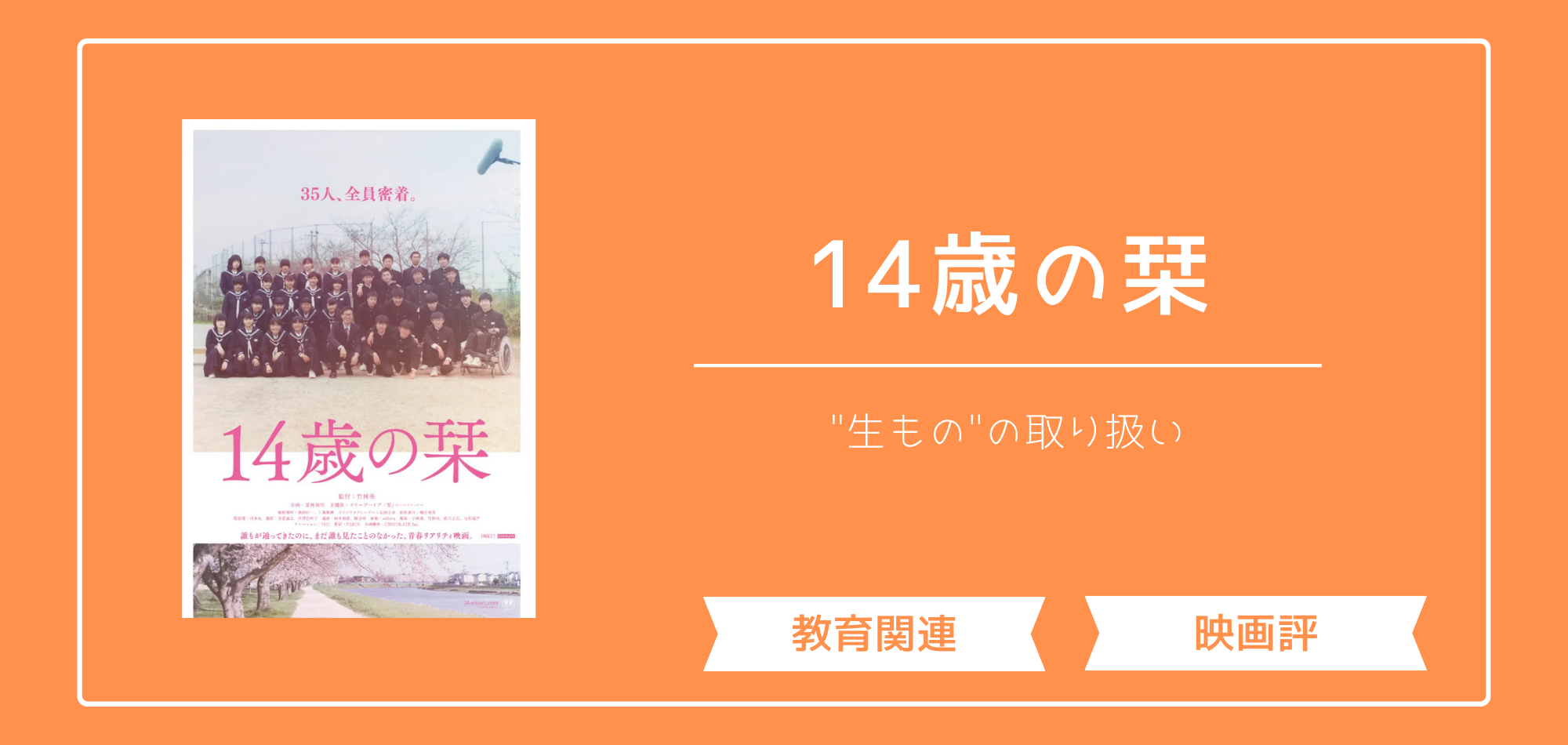本日は、リバイバル上映されている「14歳の栞」について。
今のご時世、配信サービスには展開されない映画に惹かれます。
(※ネタバレありです)
公式HPはこちら → https://14-shiori.com/
「14歳の栞」のあらすじ
『14歳の栞』は、神奈川県のある中学3年生・35人を1年間追いかけた、完全ドキュメンタリー映画です。
カメラを向けられるのが初めての14歳たちが、自分の言葉で語る学校生活・進路・家族との関係、そして「いまの自分」について——。
2020年に一度限定公開された後、SNSや口コミを通じて再び注目を集め、2024年には全国でのリバイバル上映が始まりました。
テレビや配信では届かない、リアルな14歳の“声”と“表情”。
誰もが一度は通ってきた、けれど語られることの少なかったあの時間を、静かにすくい取るような作品です。
「14歳の栞」の感想
なんとも表現しづらい感情になった為、以下2つの人格から感想をまとめてみたいと思います。
- 一観客としての私
- 心理学を学ぶ立場としての私
一観客としての私
大人とこどもの狭間の14歳のあの一瞬を保存するような、そんな映画のテーマでしょうか?
(”14歳の栞”というタイトルも粋ですね..!)
生ものを扱うときの、ひやひやしながらどきどきしながら、恐る恐る。
みたいな気持ちと姿勢で見ていました。
全体的には、
その素材の良さ、繊細さを大切にしたいからこそ、
限りなく、生ものを生のまま、提供してくださるような印象を受けました。
でもだからと言って、それを全く飾ることなく無骨に提供するのではなく、
映像の柔らかな質感、14歳当時の雰囲気を甦らせるカットの数々、
最後の川沿の桜路を35人の生徒が思い思いに歩く一本撮り等、
素敵な雰囲気のレストランとおしゃれなお皿で、”それ”をそっと目の前に出してくださる感覚。
心理学を学ぶ立場としての私
めちゃくちゃ怖い!と思ってしまいました。
大丈夫だったのかな?と。
それは現代の誹謗中傷に塗れたネット社会への危惧もありますが、
“生の自分”が世間に晒されることの14歳の心理的な影響について。
そもそも、1クラスの全員に該当する35人が映画として公開すること自体に価値がある映画だとは思うのですが、
35人全員(正しくは保護者の方の許諾も取られているかと思いますので、単純に2倍しても70人!?)が、了承するって凄すぎないですか?
きっと映像化するにあたって、
・真摯な説得、詳細なご説明
・映画冒頭に表示される「誹謗中傷はお控えください」と言った説明文言
・配信は行わない等の厳重なケア
があったのかとは思いますが、例えば
・「30人が了承しているので」と言った集団圧力はあったのではないか?
・14歳当時に発達段階として冷静に判断できず、後から振り返って後悔するようなことはないか?
等の心配が頭によぎります。
そして不登校を研究している身としては、
・本人が「不登校の要因を語りたくない」と意思表示したのに、友人が(想像ではありますが)要因を語っていたのは、本人は少なからず嫌だったのでは?
という点が一番気になってしまいました。
なんらかの葛藤や苦しさがあり、クラスに登校できず、その気持ちの整理がつかないままに
映画になることで本人にどんな影響があるのでしょうか?
おわりに
作品としては好きなのですが、心理を学ぶ人間としては、
この映画で世界に与えるインパクトよりも、
この映画で1人に深く影響してしまうかもしれないリスクの方が気になってしまいました。
しかし、実際に世に出た作品に対して、リスクの文句を言ってもしょうがないかと思いますので、
今願うのは出演したこどもたちが、出演になんらかの意味づけをして、前を向いていることだけです。
自分の言葉を話し、それが映画となり、無数の人間に届く。
その選択をしたことは間違いなく勇気がいることで、
その一歩を踏み出した14歳の皆様を私は尊敬します。
みなさまに幸あれ!