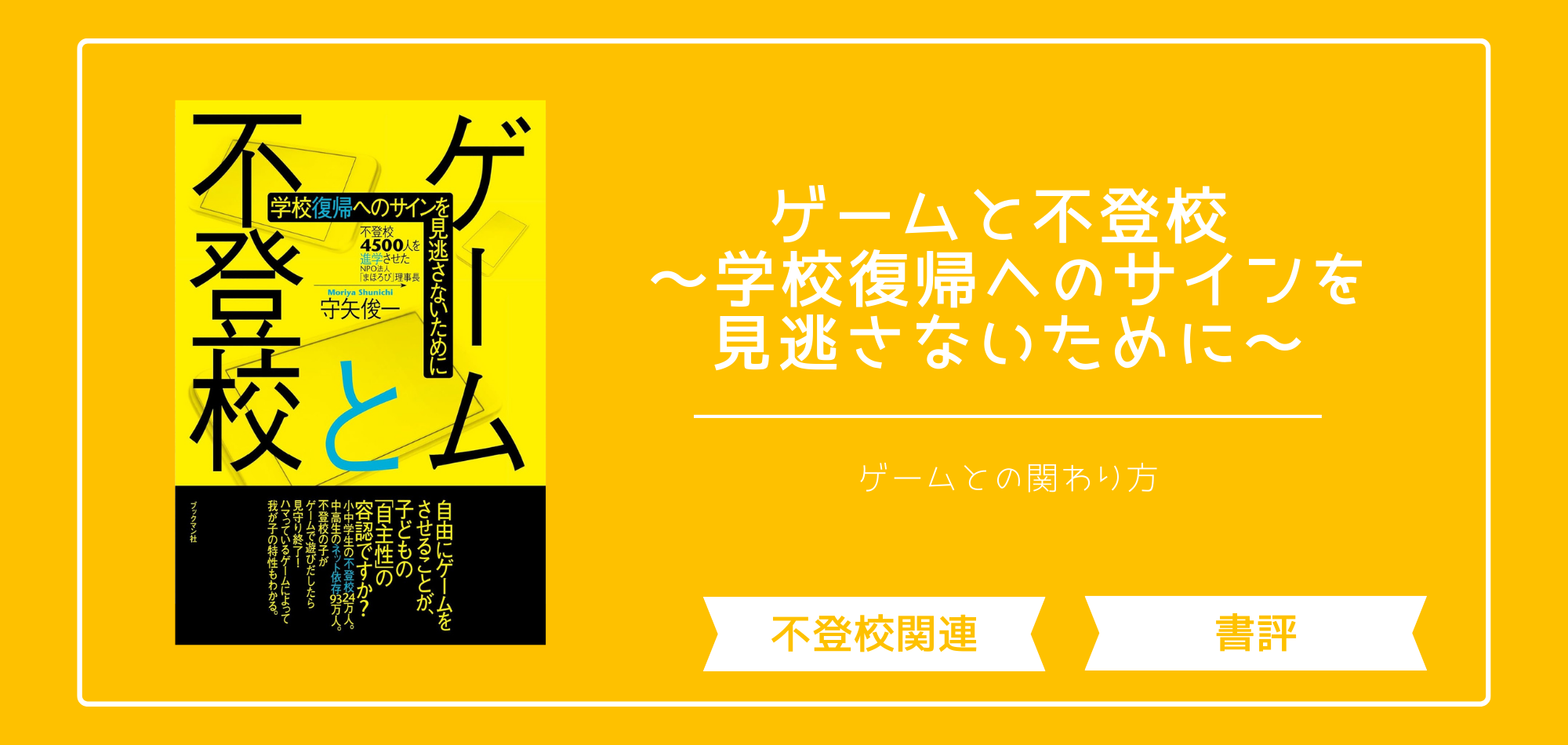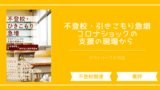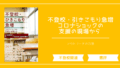今回ご紹介するのは、書籍「ゲームと不登校 ~学校復帰へのサインを見逃さないために~」。
「ゲームを好きなだけやらせることが、『自主性』の容認なのか?」
これが本書のキーメッセージかと思います。
今お子さんが学校に行かず、ゲームに夢中になっており困っている保護者の方
学校に行かないお子さんに、ゲームを渡すか悩んでいる保護者の方
そして、今実際にゲームにハマりながらも、これで良いのかな?と思っている当事者の方にも
是非読んでいただきたい一冊です。
「ゲームと不登校 ~学校復帰へのサインを見逃さないために~」のあらすじ
「無理に勉強をさせずに、好きなことをさせたほうがいいです。」
「『子どもの自主性』を信じましょう。子どもから動き出すまで待ちませんか。」
このような不登校支援に対して、著者は以下のように述べます。
ゲームにハマるのが、「我が子の自主性だと思いますか?」私の答えは、否です。
「自主性を重んじる」という言葉は、自主性をもにつけさせたいこどもたちに対して、その環境を整えた上で、地涌性を身につける方法をきちっと教えることによって確立できるものだと私は考えます。
引用:「ゲームと不登校 ~学校復帰へのサインを見逃さないために~」P.51
上記のような考えに基づきながら、
頭からゲームを否定するのではなく、ゲームとの適切な関わり方を提唱する
のが本書の内容になります。
目次
第1章 登校拒否から不登校へ―子どもの心の変化
第2章 不登校児とゲーム依存のスパイラル
第3章 不登校を終わらせるため、今すぐWi‐Fiを切ろう!
第4章 ゲームを不登校解決への糸口に使ってみる
第5章 不登校は治すもの
※少し過激なタイトルもありますが…
本書を紹介しているのは、本書のすべての内容に賛同している訳ではありませんのでご留意ください。
詳細は感想部分で少し触れられればと思います。
学びポイント
本書のメインとなるのが、第二章〜第四章にかけてのゲームとの向き合い方や、
こどもが熱中しているゲームの種類ごとのこどもの特性の把握と対策かと思いますが、
その点に興味がある方は是非実際に本書を手に取っていただければと思います。
メインの要旨は以下で一部だけ抜粋します。
不登校×ゲームの悪循環
前半は本書の内容を引用し、後半部分は私が子どもたちと関わる中で感じたことを追記しました。
▼学校への戻り方がわからない
▼その悩みを抱えつつ、長い時間を過ごすのは辛い
▼膨大な時間を楽しく過ごしたい
▼ゲームを始める
▼「依存するように作られた」ゲームにハマる
▼大人と違い、経験値が低い子どもは「このままではまずい」と気づき、止めることができない
▼ゲーム中心の生活になり、昼夜逆転が起きる
▼生活リズムの崩れにより、心身に影響が起きる
▼更に学校へ戻りにくくなる
学校に行かない状況において、どのように時間を使うのかは考えなくてはいけない内容です。
ずっとYoutubeを見ている、ずっとゲームをしていることは心身に良い影響を与えるはずがありません。
休息が必要なタイミングはあります。しかし、子どもに任せっきりでは上記負のループにハマり、
抜け出せなくなる可能性がある為、本書ではその際の対応なども記載されております。
ゲーム障害とは
ゲーム障害については、以下抜粋します。
2022年にWHO(世界保険機関)が、日常生活に支障をきたすほどゲームに没頭する「ゲーム障害」を、新たな依存症として正式に認定しました。そのうえで、次のような症状が認められるとあります。
・頻度や時間など、ゲームをプレイするうえで制御が効かない。
・ゲームの優先度が増し、ゲームをプレイすることが他の興味や日常生活よりも優先される。
・ネガティブな影響が出ても、ゲームを継続・やり込むようになる。
・ゲームの行動パターンが重度になり、その結果、自分自身や家族、社会、教育、職業といった他の重要な生活機能に支障をきたす。
上から見ていくと、上から3項目に当てはまる方は沢山いらっしゃる
上記4項目が12ヵ月以上続く場合に診断するものです。
さて、ここからはあえて、そのメイン以外にもこどもの本音という点で、私自身勉強になったことや、実際に子どもたちと関わる中で日頃感じていたことと共通する点があったので、その点を中心に取り上げます。
学校を休んでいるこどもの本音
本書ではいくつかこどもたちの本音が出てきます。
・中学生には高校生、高校生には大学や就職の話をしたり、関係する機関や場所に連れて行き、
「こんな世界も覗いてみたくない?」と持ち掛けることが不登校解決の重要なきっかけとなる・こども自身が自分の未来を現実のものとして考え出したときに初めて、
「いつまでもこのままではいられないんだ。やっぱり学校に戻らないとダメだよね?」
という問いが自分の中で生まれる
▶︎学校に行かない日々、家で落ち着く日々が続くと、保護者の方は心配になるかと思いますが
子どもたちは子どもたちなりに、考えていることが必ずあることは、子どもを信じるという意味でも重要なように思います。
・私「高校にはいくつか種類があるんだ。全日制、定時制(単位制)、通信制とあるんだけど、偏差値のことはまず置いておいて、あなたはどこに行きたいと思う?」
・子「全日制か定時制かな」ここで通信制高校を選ぶ子はゼロです。
▶︎「不登校だから、通信制高校」と考えるべきではないという趣旨の文章かと思いますが、
ある意味で「通信制高校を選ぶ子はゼロ」だとしたとき、子ども自身も通信制高校に対する偏見があるかもしれないと思いました。
とすると、フラットに子どもの意見を聞きながらも、本人が知らない情報も共有しつつ、一緒に考えることがやはり求められるのではないでしょうか。
・進路相談に乗っていくうち、不登校の子どもたちは必ずこう言います。
「別に私は、不登校じゃないから。いじめられているわけじゃないし、これから行くつもりだから!」・不登校の子たちは、「不登校」という烙印を他者から捺されたくないのです。
▶︎これはまさに感じるところです。
別途記事にもまとめたい点ではあるのですが、私は修士の研究で不登校を経験した成人の方々にインタビュー調査をしたのですが、そこで出てきたのが「”支援”に対する葛藤」でした。
「”支援”、”ケア”される対象として見られること」は心地よいものではないことは心から共感します。
この点は、学校に行っていない子どもたちと関わる人々は意識すべきことに感じます。
ゲームを不登校のとっかかりにする
私自身常に意識していることですが、お子さんと話す際、
いきなり困り事を聞かれたって答えたくはありませんし、
だからと言って大人のように天気の話をしたってつまんないですし。
じゃあどんな人間であれば、話す気が起きるか?というと、
シンプルに「この人と話すと楽しい」という感覚はとても重要なのではないでしょうか?
その際、共通する趣味はとても大事で、多くの子どもが楽しんでいるゲームはそのきっかけとして適切なのかもしれません。
不登校の理由の探り方
「探り方」等といった手法になった途端、こどもたちと真摯に向き合うのではなく、テクニックで関わるようなニュアンスになるのが嫌なのですが、探るのではなく、一緒に考えるという意味で、以下の方法や観点は有効かもしれないと感じたので、こちらで抜粋します。
・こどもの口から「退屈」「暇」「ゲームをやりたい」などの言葉が出てきたら、体調がよくなってきた証拠の為、学校を休んでいる原因を尋ねても良いとき&社会とつながる場を提案するとき
・「暇なら学校の代わりになる場所を見学しない?」「今の学校と同じような環境だとまた通えなくなるかもしれないからさ、学校の何が嫌だったのかをちょっと教えてくれる?」「(具体的な機関名を出しながら)そこの何が嫌なの?」と聞いてみる参考:「ゲームと不登校 ~学校復帰へのサインを見逃さないために~」P.198-201
診断の活用の仕方
大前提、診断を受けてお子さんの状況を理解し、
適切な対策を検討すること自体にも意味があることだと思います。
しかし、
「『診断がついたから学校にはいけないね』といった発想になってしまったら、検査は害にしかなりません。」
と著者が述べるように、診断や検査は適切な活用をしなくてはネガティブにもなりうるものだと思います。
特に、個人的には「発達障害だから/起立性調整障害だから」といった「レッテル」は、
本人にも周囲の人にも個別性を軽視し、可能性を狭めるリスクもあるため注意が必要ではないでしょうか。
その意味では、「診断」も「ものすごく重要な事実が発覚した」と受け止めるのではなく、
自分らしく生きやすくする為に「活用するもの」として以下のように使うのは一つの方法のように感じました。
発達障害や起立性調整障害、過敏性大腸炎などの病名は学校を休むための理由ではなく、
学校に戻って友達と話をする際に、「長期で学校を休んでいた理由」として使います。
感想
ちなみに…不登校については本当にさまざまな思想があるように私は感じているのですが、
本書の基本思想は「学校は行くもので、行かせるもの」です。
上記もしましたが、私が本書を取り上げるのは、上記思想に賛同しているからではありません。
私の基本的な考え方は、一貫して「場合による」のではないか、です。
こどもの性格によっても、こどもの特性によっても、こどもを取り巻く環境(家庭、学校)によっても、望ましい対応の仕方は異なると思っております。
例えば、本書では「文部科学省は『学校は社会性を学ぶところだから、少しくらい嫌なことがあっても、それに立ち向かうための努力をすることは生きていくために必要なことです』と言っていくべきです。」と書かれておりますが、私は以下のようないくつかの観点から賛同はできません。
・”少しくらい嫌なこと”の程度は本人と周囲の人間では判断が異なる場合があり、上記メッセージを伝えることで、周囲の人間が本人の辛さを軽んじて、学校に行くことを強制させるリスクがあるのではないか
・上記同様に”立ち向かう努力”の難易度は当人の個性と環境の整合性により異なることを考慮するべきではないか
・今は学校ではない場であっても社会性は学ぶことができる為、学校を唯一解としなくても良いのではないか
もちろん、傷ついてもおらず、努力ができる状態にも関わらず、
踏み出せていないこどもには上記のメッセージが重要なことも多いにあると思います。
また、文部科学省が上記メッセージを発するべきという主張は、
そんな傷ついていない不登校の生徒たちが圧倒的に多いという理解なのかと思うのですが、
本当にそうなのでしょうか?
国の政策を決める立場にはない、というポジショントークではありますが、
目の前の唯一無二の子どもに向き合いたい私としては、
たとえ99人にとって必要なメッセージであっても、目の前の1人にとっては傷つく可能性があることを常に考慮し、
1人ひとりを見つめながら、伝えることも、対応することも、ともに考えていきたいと思います。
おわりに
少し話がそれましたが、本書の中で海外のゲーム制限について取り上げられており、最後に少し触れられればと思います。
海外では未成年者をゲーム依存から守る為に、近年、以下のような制限を設けているとのことです。
・アメリカでは、2013年にインターネット・ゲーム依存症に「障害」としての基準を設定
・韓国では、2011年から未成年者の夜中のゲームを禁止
・中国では、2021年8月、コロナ禍の最中に18歳未満のユーザーがオンラインゲームをする時間に新たな制限を設定(未成年のオンラインゲームユーザーは、祝日、金曜日、土曜日、日曜日の午後8時-午後9時までしかプレイできない)参考:「ゲームと不登校 ~学校復帰へのサインを見逃さないために~」P.64
それだけ中毒性がある危険なものであるという認識が、まだまだ自分には浅いことを実感するとともに、
大人である私でも理解していないのに、
こども、そしてさらに辛い状態で冷静に考えることができないこどもが
適切な判断などできないのではないか?
ということは、本当に意識しなくてはいけないことだなあと思いました。
現代のこどもの生活を考えたときに、避けては通れないゲーム問題。
本書をきっかけに、改めて考えていただければと思います。