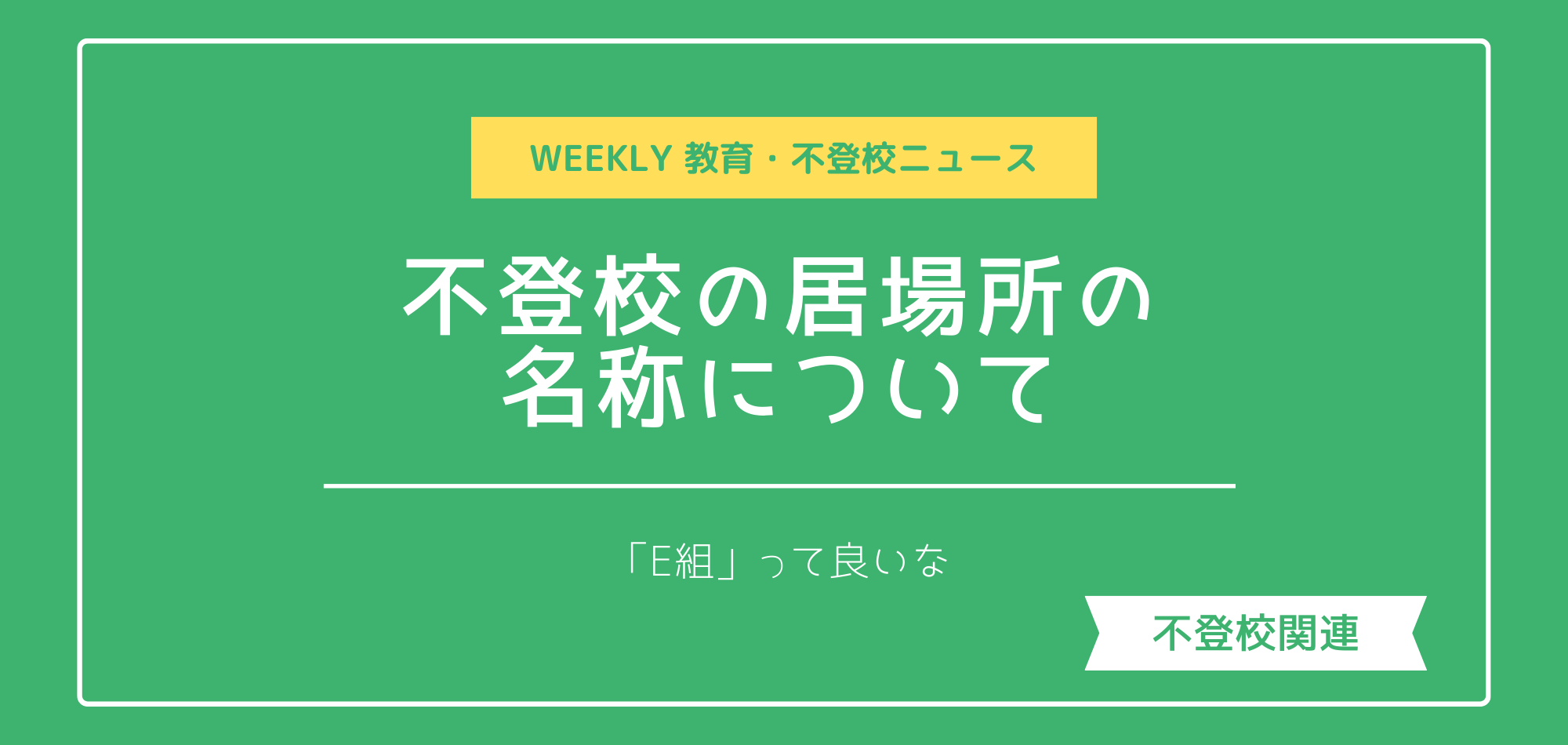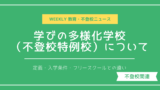新年度が始まり、さまざまな教育の話題が注目される中で、Yahoo!ニュースにこんな記事が掲載されました。
「カルチャーショックを受けた」公立小の校長が「不登校児童のためのE組」をつくった理由
この記事では、NPO法人「福祉広場」代表・池添素さんと、小学校校長・牧紀彦さんとの対話を通して、不登校の子どもたちのために学校の中に“居場所”を設けた経緯を紹介しています。
その中で私が気になったのが、「E組」という居場所の名前でした。
今回は、この「E組」という名称に着目しつつ、
不登校の子どもたちのための場所に、どんな名前がふさわしいのか?
その名前が纏う“空気”や“意味”について、考えてみたいと思います。
校内教育支援センター(スペシャルサポートルーム等)とは?
まず、校内教育支援センター(いわゆるスペシャルサポートルーム)は、不登校の児童生徒が安心して過ごせる為の、学校の中に設置された場です。主に保健室や空き教室を活用し、個別の学習支援や休憩、交流などを行うことが目的とされています。
通常の教室とは違い、少人数または個別対応が可能で、学校復帰や家庭以外の居場所づくりの一環として整備が進められています。
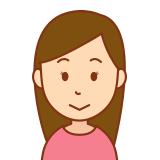
校内教育支援センター(スペシャルサポートルーム等)についても、今後詳細に別途記事でご説明できればと思います!
E組という名称について
さて、ここから校内居場所の名称について考えていきます。
E組の由来
本ニュースで取り上げられた「E組」という学校内居場所の名称について、以下のような記載があります。
E組は大人がネーミングしたわけではない。大人たちは当初は「居場所」と呼んでいたが、「いばしょ」の「い」なのか、子どもたちが「E組」と呼ぶようになった。牧さんは「何のEかわからないんですよ。『いいね』のいい? それも含まれているかな。『何をしてもいい』の、いい、なのかもしれません」とほほ笑む。
名称が与える印象
たかが名称、だと思いますか?
個人的にはどんな名称であるかは、通うこどもたち・通わないこどもたち両者にとって
「そこに行くことがどんな意味を持つか?」を規定する一つの要因になる為、十分に考慮すべき事柄に感じます。
例えば、以下のような名称はより適切な名称にすることが求められ、変更されております。
- 適応指導教室 → 教育支援センター
- 不登校特例校 → 学びの多様化学校
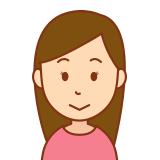
適応指導教室は、”学校に適応することを指導する教室”、
不登校特例校は、”不登校の子どもたちの為の特例の学校”
というようなニュアンスに聞こえてしまいかねません。
“E組”、という”特別”じゃない名称
その意味で、なんだか意味はわからない、けれどふんわりポジティブなニュアンスを纏った「E組」
という名称は、私はとても良いなと思いました。
実際に本当にちょっとしたことが重なったが為に学校に行けなくなることがある。
(もちろんすごく辛い思いをして、ということも多々ある。)
おわりに
特に名称については、日々思うところがあることだった為、少し長くなってしまいました。
全然気にしないよーっていう子もいれば、気にする子もいると思うのです。
その場合、やっぱり”気にするかもしれない”という視点は持っておきたいですよね。
名称に限らず、感度を上げておきたい。自戒を込めて。